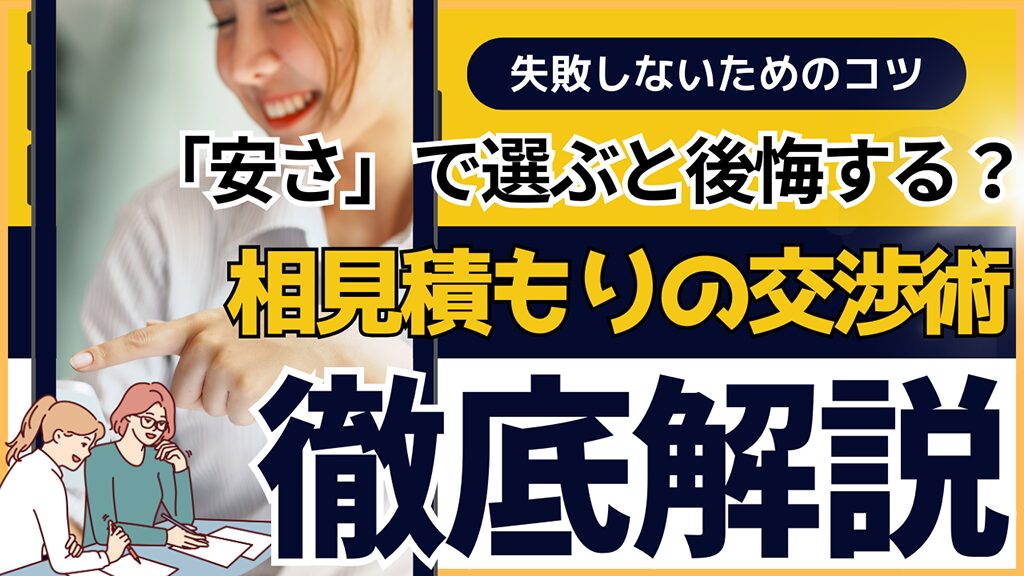

執筆者:後藤ようこ
見積もり集めのコツ「安さ」で選ぶと後悔する?相見積もりで失敗しないための本音ガイド 〜『相見積もりで価格の安い業者さんを選ぶ』は、 交渉としてすでに負け〜
- 2022年09月24日
- ノウハウ
- パンフレット制作のコツ・ 見積もり

執筆者:後藤ようこ
後藤 ようこ取締役副社長
スキル
- ランディング(執筆)
- ディレクション
- コンサルティング
大学病院で看護師として働いたのち、看護教員の資格を取得し看護教育に携わりました。
現在は株式会社ノーブランドの取締役としてウェブサイトやパンフレット制作のディレクションを担当しています。(ディレクションは20年以上の経験を持ちます。)
また、医療系の出版社で医療記事の連載をした経験があります。医療記事をはじめ、販促物に掲載する原稿作成(ライティング)も担当しています。医療知識を持っているため、医療、介護、福祉関係のお客様が多いです
これまで学んできた、教育学、人間関係論、心理学などの知識を活かし、販売促進に関わるコンサルティングも行っています。
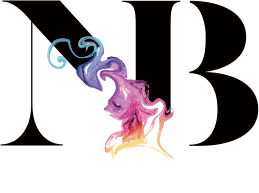
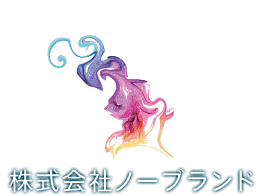
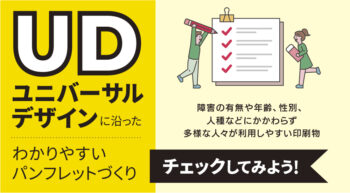 ユニバーサルデザインに沿ったパンフレットづくり 〜チェックしてみよう〜
ユニバーサルデザインに沿ったパンフレットづくり 〜チェックしてみよう〜 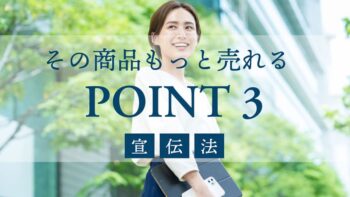 その商品はもっと売れる!買い手に選んでもらうための宣伝方法3つのポイント
その商品はもっと売れる!買い手に選んでもらうための宣伝方法3つのポイント 

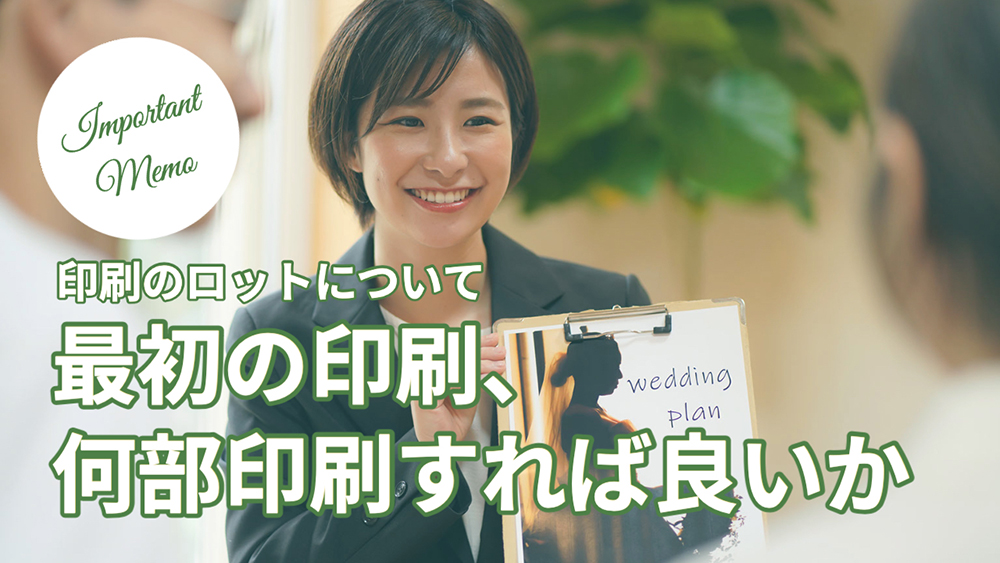
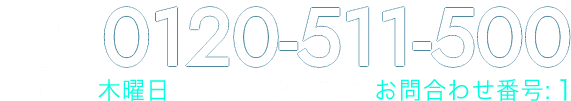
<記事の概要>
カタログやパンフレット制作を依頼する業者選択時、見積もり収集時の交渉術や相見積もり時に注意しなければならない12ポイントをまとめました。目 次
1相見積もりをとるのは難しいのです
「カタログ制作をお願いできる会社を探して」と上司に言われたけれど、正直どこから手をつければいいか分からない――そんな経験はありませんか?
実際、相見積もりで「安くて良い会社を選ぶ」のは、簡単なことではありません。
私たちは、パンフレットやカタログを専門に29年間制作してきました。これまでお付き合いしてきたお客様の数は、なんと数百社以上にのぼります。(※お客様のご感想は「リアルな声」でご覧いただけます。すべて実際の声を掲載しています)
リアルな声
「業者さんと合わなかったらどうしよう」「プロジェクトが途中で止まったら…」
そんな不安を抱えるのは当然のことです。
デザインや印刷のことは、やっぱり専門家に相談するのが一番。
このコラムでは、29年の経験をもとに、相見積もりをうまく活用しながら、自分に合った制作会社を見つけるヒントをお伝えしていきます。
もちろん、「うちに頼んでください!」という営業トークではありません。
少しでもみなさんの不安が和らぎ、納得のいく選択ができるよう、フラットな立場でお話ししていきます。
2見積もり依頼でよくあるケースと、相見積もりの正しい使い方
私たちのもとには、日々たくさんのカタログやパンフレット制作に関する見積もり依頼が寄せられます。
その中で時折、こんなふうに言われることがあります。
もちろん、複数社の見積もりを比較する「相見積もり」は、昔からよく使われている方法ですし、活用の仕方によってはとても有効です。
ただし、いくつか注意すべきポイントがあることをご存じでしょうか?
相見積もりで比較が成立するのは、「まったく同じ条件・内容」で依頼した場合に限られます。
たとえ小さな違いでも、仕様や前提条件が異なれば、出てくる見積もりも当然バラついてしまいます。
つまり、「見積もりを並べて価格を比較するだけ」では、正確な判断ができない可能性があるのです。
これから先は、カタログやパンフレット制作における相見積もりの正しい取り方や、注意しておきたいポイントについて、わかりやすく解説していきます。
3金額だけで比較すると失敗します
だからこそ、制作会社によって仕上がりや提案の内容、関わる人材のスキルや実績が大きく異なります。
たとえば、フリーランスのデザイナーさんにお願いすれば、1人で企画から制作まで対応するケースが多いでしょう。
一方、大手の広告代理店に依頼すれば、プロデューサーやディレクター、デザイナー、コピーライター、カメラマンなど、複数のプロフェッショナルがチームで対応してくれます。
このように、同じ「カタログ制作」でも会社によってやり方も仕上がりも全く違うのです。
ですから、金額だけを見て「こっちが1万円安いから」と判断してしまうと、後で「思っていたものと違った…」という失敗につながることがあります。
特に注意したいのは、デザインは“既製品”ではないということ。
完成するまで実物が見えないからこそ、関わるデザイナーの得意分野や経験が、仕上がりに大きく影響します。
安さだけで判断してしまうと、結果的に思ったようなものができず、修正や作り直しに費用がかかってしまう…なんてことにもなりかねません。
「見積もり比較」はもちろん大事ですが、数字だけでなく、
つくってくれるのか?
という視点も、しっかり持っておくことが重要です。
弊社では
4“相見積もりなので安くして”がダメな理由
相見積もりをお願いしたときに、
「他の会社より高ければ、そちらにお願いしないかもしれません。なのでできるだけ安くお願いします」
…つい、そんな風に伝えたくなる気持ち、よく分かります。
でも実は、この言葉――制作会社側から見ると、かなりネガティブな印象を与えてしまうんです。
なぜなら、制作会社としては、最初から「適正価格で、品質に見合った提案」をしているつもりだからです。
私たち制作会社も、無理に高く売ろうとは思っていませんし、むしろ「どうやったら予算内で、できるだけ良いものをつくれるか」を常に考えています。
ただ、「安くしてください」とだけ言われると、こうなってしまう可能性があります。
それでは本末転倒。「安くしてもらった」はずが、「価格相応の品質になってしまった」――という状況を、自分で招いてしまうことにもなりかねません。
とくに、品質にこだわっている会社ほど、「価格だけで判断するのであれば、他をお探しください」とやんわり断られることもあります。
本当はすごく良いものを作ってくれる会社だったのに、その一言で候補から外れてしまう…なんて、もったいないですよね。
もちろん、「予算が限られている」というのは正直な悩みです。
だからこそ、伝え方を少し変えるだけで、見積もりの内容もグッと前向きなものになることがあります。
その工夫については、次の章で紹介していきます!
5実際にあった、こんな失敗
過去にあった、実際の事例をご紹介します。
あるお客様にお見積もりを提出した際、「他社と比べて印刷費が高いのはなぜですか?」というご質問をいただきました。
確かに、他社よりも印刷費の項目が高く見えたのですが、実はその背景には明確な理由があったのです。
そのお客様はアパレル業界の方で、商品の色味がカタログ上で正確に再現されることが非常に重要でした。
私たちはその点を考慮し、「スクリーン線数の高い高品質な印刷方式」と「本番印刷前の色確認(本機校正)」を含めたご提案をしていました。
一方、他社はスクリーン線数の低い「格安印刷」を選択しており、校正工程も含まれていなかったため、印刷費が安く抑えられていたのです。
もしこの工程を省いてしまったら、仕上がりの色味が実際の商品とズレてしまう恐れがありました。
特にアパレルや化粧品など「色にシビアな業種」では、このズレが大きなダメージになることもあります。
実際、こうした工程を省いたばかりに「色が全然違う」「印刷し直しに…」という失敗は少なくありません。
私たちは、そうしたリスクを事前に避けるため、最初から必要な工程を含めたお見積もりを提示していた、というわけです。
つまり、見積金額だけを見て「高い」と判断するのではなく、「何が含まれていて、なぜその金額になるのか」まで確認することが大切なんです。
業界特有の知識やノウハウをもとにした提案は、やはり“プロならでは”。
こういった部分にこそ、信頼できるパートナーかどうかの判断材料が隠れているのです。
6相見積もりで安くしてもらうために補足する言葉とは
「少しでもコストを抑えたいから、相見積もりで価格を比較したい」
これは、多くの企業にとって自然な考え方です。
でも、単に「安くしてください」とお願いするだけでは、先ほどお伝えしたように、クオリティを下げるリスクを自分で招いてしまうかもしれません。
では、どう伝えればいいのでしょうか?
実は、ちょっとした一言を加えるだけで、見積もりの内容も印象も大きく変わります。
たとえば、こんな言い方はいかがでしょう。
このように伝えると、制作会社側も「きちんと評価されている」と感じ、価格だけでなく、サービスや品質面も丁寧に説明してくれることが多いです。
ポイントは、「価格だけを見て判断するつもりではない」という姿勢を見せること。
そうすることで、相手も誠実に対応してくれますし、「この案件は本気だな」と前向きに捉えてくれるはずです。
相見積もりは、うまく使えばとても有効な手段。
だからこそ、伝え方ひとつで、より良い提案やパートナーとの出会いにつながるんです。
7カタログ、パンフレットの見積もりを集める時の注意点、12個
業界の特性上、同じ項目でも記載方法や表現が違っていたり、詳しい説明がなかったりすることもあります。
そのため、表面的な数字だけでは比較が難しいのが実情。
きちんと各項目の内容を把握し、比較検討することがとても重要です。
以下は、特にチェックしておきたい12のポイントです:
1.基本デザイン料金
パンフレットやカタログ全体のデザインにかかる基本料金です。加えて、1ページあたりの制作費が別途かかるケースも多いです。サイズやページ数によって変わりますので、仕様を正確に伝えましょう。
2.提示してくれるデザイン案の数
初回提案で何案出してもらえるか確認しましょう。1案のみか、複数案かで料金が変わることがあります。
3.文字校正料金
誤字脱字などのチェック作業の料金です。校正が見積もりに含まれていない場合もあるので確認が必要です。
4.原稿作成料金(ライティング)
原稿を業者が書いてくれるか、自社で用意する必要があるかで大きく変わります。ライターの有無も確認ポイントです。
5.訪問対応の有無と料金
担当者が直接訪問してくれるのか、訪問回数に制限はあるのか。オンラインでの打ち合わせの回数制限や料金などの対応範囲もチェックしておきましょう。
6.修正回数
制作中に対応してもらえる修正回数の上限は必ず確認しましょう。無制限と記載されている場合は、その分の工数が料金に含まれている可能性もあります。修正回数が超過した場合の追加料金なども確認しましょう。
7.イラスト作成料金
オリジナルイラストの作成が可能なのかどうかと、その制作費を確認しておきましょう。素材サイトで対応する会社も多いですが、オリジナルが必要な場合は費用がかかります。
8.写真撮影料金
カメラマンによる撮影が必要かどうか。プロのカメラマンを派遣してもらえるか、その料金はいくらか、撮影した画像の著作権の取り扱いも確認しましょう。
9.印刷料金(細かい条件)
サイズ、ページ数、紙質、加工、部数、スクリーン線数などの条件をきちんと確認しましょう。少し条件が違うだけで金額が大きく変わることもあります。
10.色校正料金
本番印刷前に色味を確認する色校正という工程が含まれているか確認しましょう。一般的な会社案内パンフレットの場合は割愛しても問題にはなりにくいですが、特に色が重要な業種では必須です。
11.イメージ写真使用料
カタログやパンフレットに使うイメージ素材の使用料を確認しましょう。フリー素材で済むか、購入が必要かも確認が必要です。素材サイトはどのようなサービスを使っているかもわかると、よりベターです。
12.画像の補正・加工・トリミング料金
写真を美しく見せるための作業費が見積もりに含まれているかも確認しましょう。画像加工の点数が多くなるほど、費用が別途計上される場合もあります。複雑な画像加工なども別料金がかかる場合があるので、事前に確認しましょう。
8必ず実績を見よう
カタログやパンフレットなど、いわゆる商用デザインには、「これが正解」という明確な基準はありません。
けれど、お客様が「いいね!」と思えるものに仕上がること、それがすべてのゴールです。
ただし、“どんなデザインでもOK”というわけではありません。
商用印刷物には、最低限守るべき“ユーザビリティ”があります。
たとえば:
カタログやパンフレットは、営業活動をサポートする大切なツール。
配った相手の心をつかみ、商品やサービスに興味を持ってもらわなければ、成果につながりません。
そのためにも、「この会社は、どんな実績があるのか?」を必ずチェックしましょう。
見極めのポイントはとてもシンプルです。
デザインの専門知識はいりません。
自分が「このカタログ、読みやすいな」「印象に残るな」と思えるかどうか、フラットな目で見るだけで大丈夫です。
デザインの美しさだけでなく、
“読み手の気持ちに寄り添った提案”ができている会社かどうか――
その判断材料は、過去の実績にしっかり表れています。
9まとめ|相見積もりで“後悔しない”ために大切なこと
カタログやパンフレット制作で相見積もりを取るのは、決して間違いではありません。
ただし、「価格だけ」で判断してしまうと、本当に大切な“品質”や“信頼できるパートナー”を見落としてしまう危険もあるんです。
そこで大切なのは、以下のポイントを意識すること:
相見積もりは、同じ条件で依頼することが基本
価格だけでなく、工程・品質・サポート体制も比較する
「できるだけ安く」ではなく、「納得できる理由」で交渉を
見積もり内容は細かく確認し、不明点は必ず質問する
制作実績を見て、その会社の“強み”や“スタンス”を見極める
そして何より、「パートナーとして信頼できるかどうか」を見極める視点を持つこと。
良い制作会社は、予算や要望に対して誠実に向き合ってくれます。
あなたのプロジェクトが、後悔のないスタートを切れるように――
この記事が、その一歩となれば嬉しいです。